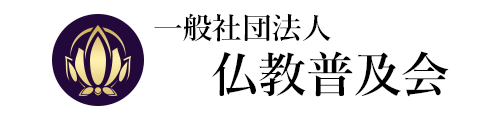誰もが知ってる「カルピス」は仏教用語?!
こんにちは。仏教普及会 釈です。暑い日が続いていますが、食欲は落ちていないでしょうか?暑くなると口当たりがよくて冷たいものが欲しくなりますよね。そういえば、夏に冷蔵庫を開けると必ず「カルピス」がありました。今日は夏になると食べたくなる「かき氷」とかき氷にかけると美味しい「カルピス」についてお話します。
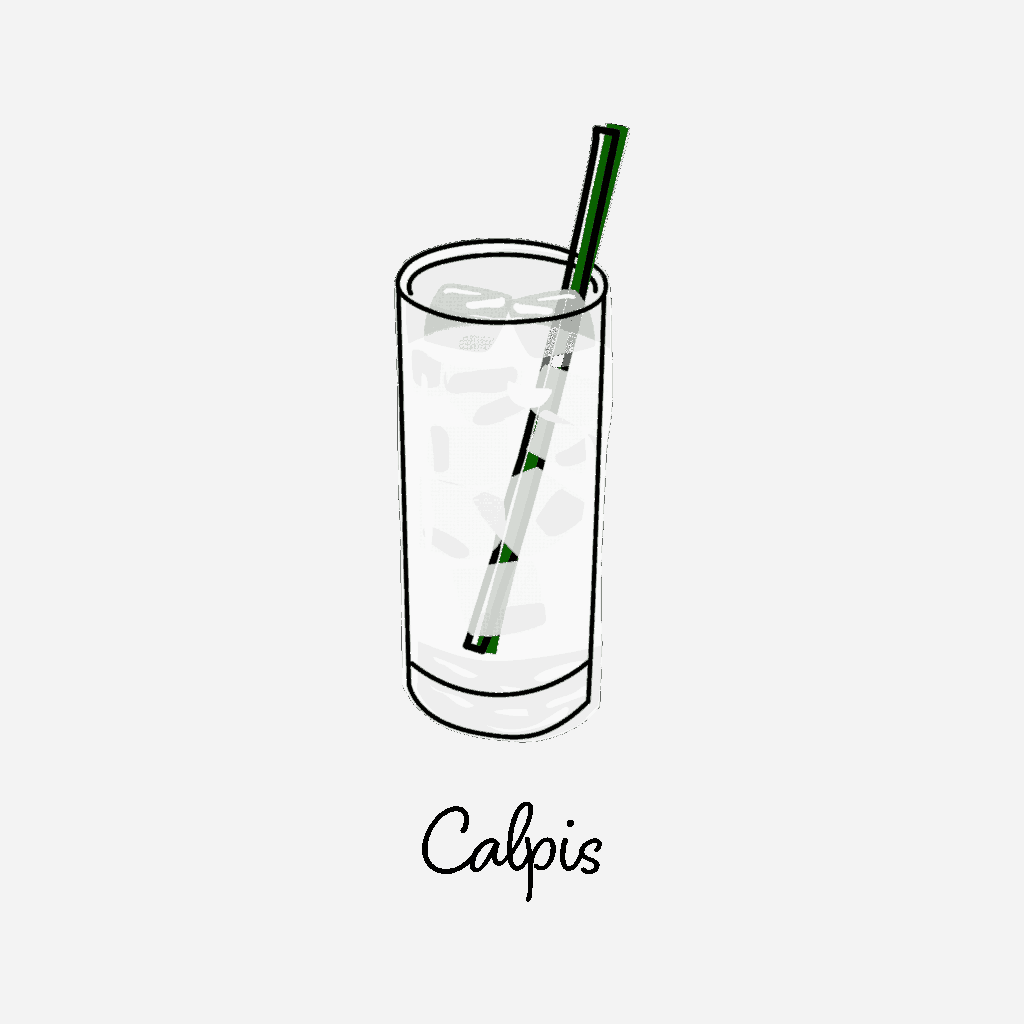
「カルピス」は仏教用語?
カルピスの創業者である三島海雲氏は、浄土真宗本願寺派のお寺の息子として生まれ、仏教の教えを学んでいました。体に良く、美味しい飲み物を提供したいということから「カルピス」は開発されました。
カルシウムの「カル」、「ピス」はサンスクリット語の「サルピス」から取って命名されました。サンスクリット語の「サルピス」は、仏教における牛乳を精製する過程の五味の一つで、熟酥味を指します。
「熟酥味」は、仏教用語である「醍醐味」の語源となった言葉の一つで、カルピスの名前には、仏教の教えである五味や、最高の味を意味する醍醐味が込められています。
特権階級にしか口にできなった「氷」
巨峰、白桃、メロン、パイン、マンゴーと何種類もあるカルピスですが、私の子供の頃はカルピスの味は一種類しかありませんでした(笑)これだけ種類があれば、かき氷機が家にあれば、お手軽にかき氷が楽しめますよね。
そんな今は簡単に口にできる氷ですが、昔は一部の特権階級にしか口にできなかったのはご存知でしょうか?夏に氷を求めるにはあらかじめ冬の雪や氷を氷室で保存する以外に方法が無かったからです。
平安時代に清少納言の『枕草子』では「あてなるもの」(上品なもの、良いもの)の段に、金属製の器に氷を刃物で削った削り氷(けずりひ、文中では「けつりひ」)に蔓草の一種である甘葛(あまかづら・あまづら、蔦の樹液または甘茶蔓の茎の汁)をかけたとしてと記述されています。


氷の神様を祀る「氷室神社」
奈良にある氷室神社は奈良時代、豊作祈願の祭祀が営まれ、今では毎年5月1日に大型氷柱や花氷を奉納する「献氷祭」が執り行われています。夏には「かき氷献氷」もあり、参拝後に純氷のふわふわのかき氷を楽しめます。
| 名称 | 氷室神社 |
| 住所 | 〒630-8212 奈良県奈良市春日野町1−4 |
| 電話番号 | 0742-23-7297 |
| アクセス | ・車とバスをご利用の場合 JR奈良駅・近鉄奈良駅から奈良交通の市内循環バス外回り 約5~10分、氷室神社・国立博物館前にて下車すぐ ・徒歩の場合 近鉄奈良駅から東へ約15分 |
| 営業時間 | 月曜日 6時30分~17時30分 火曜日 6時30分~17時30分 水曜日 6時30分~17時30分 木曜日 6時30分~17時30分 金曜日 6時30分~17時30分 土曜日 6時30分~17時30分 日曜日 6時30分~17時30分 |
| URL | https://himurojinja.jp/pray/ |
いかがでしたでしょうか?かつては貴族や上流社会の特権階級にしか食べられなかった「かき氷」。いまは変わり種のかき氷なんてものも存在していて、思いきり堪能することができます。暑く過ごしにくい日々が続いていますが、体に良くて美味しい「カルピス」をかけたかき氷でも食べて、のんびり心豊かに贅沢気分を味わうのはいかがでしょうか。
参考:https://ja.wikipedia.org/wiki/かき氷#歴史
一般社団法人 仏教普及会|大阪・関西完結葬のことなら090-9252-3917受付時間 :24時間対応 土日祝OK
お問い合わせ お気軽にお問合せください。