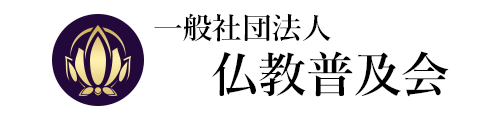最近、高齢者の孤立生活や、コロナ禍以降ご高齢者とお子様が離れて暮らすことが増え、近くに頼りになる身内の方がいないご高齢者が一人で生活し、身寄りのないご高齢者が増加しています。そのような場合第三者が後見人となることが多いのですが、ではそのような時に被後見人が亡くなられたらどのようにしたら良いのでしょうか、後見人の皆様の中には被後見人が亡くなられた時どのように対処してよいのかわからない方もお見えかと思いますので、後見人の制度や対応についてまとめています。

成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。
法定後見制度では、家庭裁判所が個々の事案に応じて成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し、その権限も基本的に法律で定められているのに対し、
任意後見制度では、本人が任意後見人となる方やその権限を自分で決めることができるという違いがあります。
近年増加している身寄りのない方の葬儀の在り方
近年核家族化やコロナ禍以降ご家族が離れて暮らすケースなどがあり、結果的にご年配者が孤立して生活する事が増加しています。又それ以外にも既に死別や疎遠となって身寄りのないご高齢者も増えております。
身寄りのない方が一人で生活する事は認知症などを発症した場合の法律判断の不安や悪徳商法に引っ掛かるなどのリスクが内在していため、後見人を定める必要があります。
しかしながら、後見人は被後見人の生前の生活をサポートする事が法律上の定めとなっているため、被後見人が死亡した場合火葬や納骨を行う義務はありません。とはいえ身寄りのない方の場合、一律的に役所にお任せするのも感情的なものもありなんだか割り切れない気持ちになります。ではどうしたら良いのでしょうか


家庭裁判所の許可
「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」は平成28年10月13日に施行されて、成年後見人は、成年被後見人の死後も、一定の範囲の事務を行うことができることとされました
成年後見人が死後事務を行うためには次の要件が必要となっています。これは、本来成年被後見人の死後は、その権利義務は全て相続人に引き継がれて、成年後見人の権限は失われるのが原則だからです。
- 成年後見人がその死後事務を行う必要があること
- 成年被後見人の相続人が、相続財産を管理することができる状態に至っていないとき
- 成年後見人が当該死後事務を行うことについて、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかな場合でないこと
- 民法873条の2第3号の死後事務(前記遺体の火葬・埋葬の契約など)を行う場合は、さらに家庭裁判所の許可が必要
死後事務任意契約
「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」により家庭裁判所の許可があれば後見人が火葬を執り行うことは出来ますが葬儀までは認めていません。ではどうしたら良いのでしょうか
身寄りがなく、自ら亡くなった時ご心配の方は生前に後見人との間で「死後事務任意契約」を結んでおくことで後見人に葬儀をお願いすることができます。
後見人の皆様へ
身寄りのない方の後見人になられている方は、被後見人がお亡くなりになられた時にいざ色々な手続きをすることとなると準備が大変です。まして火葬や納骨などをその時になって手配すると思いがけず
費用が高額だったなんてこともあるかと思います。一般社団法人 仏教普及会は、このような時でも27万円で火葬から納骨まで一括して執り行いますので、火葬後の骨壺をどうしたら良いかなどの心配もございません。
安心してお任せください。

一般社団法人 仏教普及会|大阪・関西完結葬のことなら090-9252-3917受付時間 :24時間対応 土日祝OK
お問い合わせ お気軽にお問合せください。