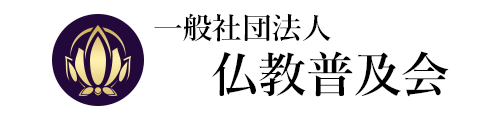お供え物としても良い「スイカ」
暑い日が続きますね。仏教普及会の釈です。毎日熱帯夜、真夏日が続いております。体調管理には十分ご留意下さい。さて本日は「スイカ」についての記事を書こうと思います。
実はスイカはお供え物としても良いというのはご存じでしたか?

仏教では丸いものは縁起が良いものとされています。
お盆が近づいてきましたが、お供え物として実は「スイカ」も良いものとされています。仏教では「人の縁(えん)」と丸いもの「円(えん)」をかけて良いものとされています。
スイカはもちろんメロンなども良くお供え物等で利用されるのはそのためです。故人やご先祖様との縁が切れないようにといった意味合いが込められています。
スイカはちょっと重いですが、近年はたくさんの品種が出ており、小さめのスイカもありますのでお供え物の一つの選択肢として考えられても良いかと思います。
スイカが日本に伝わったのはいつ頃から?
日本に伝わった時期は定かではありませんが、色々な説があります。西方から中国(唐)に伝わったスイカが、平安時代に日本に渡ったといわれています。天正7年(1579年)、ポルトガル人が長崎にカボチャとスイカの種を持ち込んだ説や、慶安年間隠元禅師が清から種を持ち込んだ説があります。
『農業全書』(1697年)では「西瓜ハ昔ハ日本になし。寛永の末初て其種子来り。其後やうやく諸州にひろまりました。」と記されています。一方、『和漢三才図会』では慶安年間(1648年 - 1652年)に隠元禅師が中国大陸から持ち帰った説をとっています。平安時代末期から鎌倉時代初期に成立したとされる国宝『鳥獣人物戯画』には、僧侶の装束をまとったサルのもとにウサギが縞模様をした作物を運んでいる姿が描かれた図絵があり、これが確認できる日本最古のスイカらしきものと言われています。
江戸時代初期には栽培が広がりを見せ、『農業全書』(1696年)には「肉赤く味勝れたり」と記述されていて、初期のスイカは黒皮系の品種で江戸時代にはすでに販売されていました。日本全国に広まったのは江戸時代後期です明治時代になるとアメリカ・ロシア・中国(清)からの新種導入が盛んになり、アメリカから「アイスクリーム」「マウンテンスイート」「ラットルスネーク」などの品種が導入されました。


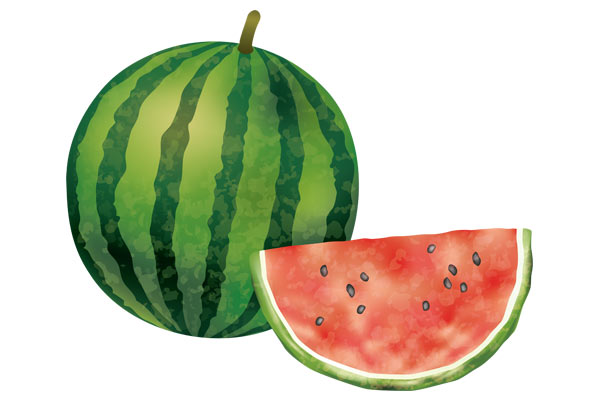
夏バテ防止、疲労回復にスイカの魅力的な効能
スイカの甘味は果糖で、冷やしすぎると舌が甘味を感じにくくなるので、食べる2~ 3時間前に冷やすのが理想とされています。
果肉や種子に含まれるカリウムはむくみ解消ならびに利尿作用があるため、暑さで体力を消耗し水分を過剰摂取することで起こりがちな夏バテに効果があるとされています。カリウムは血圧を下げる効果があります。
スイカから発見されたアミノ酸の一種で、他のウリ科の作物にも含まれるシトルリンもまた、血管拡張による冷えの改善に加え、むくみ解消や利尿作用の効果があるといわれ、特にスイカの果皮に多く含まれています。赤い果肉の色素は、抗酸化作用がある
カロテノイドのβ-カロテン、リコピンが豊富に含まれていることで生活習慣病防止に役立つと考えられています。その他にもスイカに含まれるシトルリンは疲労回復に効果があると言われています。
いかがでしたでしょうか?意外と知っているようで知らない「スイカ」ですよね。私自身もスイカの歴史については調べてみて色々な説があり伝わった時期が不明瞭なのは少し驚きました。「丸いもの」が縁起が良いのはご存じでしたか?いつものお供えで同じものばかりを選んでしまっている。。。そんな時には「スイカ」を選んでみてはいかがでしょうか。又ご家族の皆様はこれから夏休みに入りますので、皆様で「スイカ割り」をお楽しみなられるのも夏の人時の良い思い出になるのかと思われます。